TOP >> WEBコンテンツ >> 全国映画よもやま話 >> 香ばしい煙
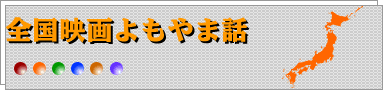
香ばしい煙…家へ帰れる幸福 (映画『野火』から)
2015年8月14日 朝日新聞 朝刊
香ばしい煙…家へ帰れる幸福
フリーランス記者 平田 剛士
_まだ日も高い午後3時過ぎ、住宅街のあちこちから、もくもく白い煙が立ち上り出す。軒先で盛大に煙を立てつつ味わう焼き肉こそ、北海道の夏の郷土食だ。
_風の向くまま入れ替わり漂ってくる香りに、家路を急ぐ自分のおなかもぐうっと鳴る。あぶられて溶けた脂が木炭に触れてジュッと弾ける様子が目に浮かぶ。
_そんなたわいない条件反射がどれほどかけがえないか。映画『野火』(塚本晋也監督)に教えられた。戦争の実像を遮るベールを剥がした作品で、見るにはそれなりの覚悟がいる。
_原作は、大岡昇平(1909~88)が51年に発表した同名小説である。70年前のきょう、1945年8月14日は、日本政府がアジア・太平洋戦争の無条件降伏(ポツダム宣言)を受諾した記念日だが、映画はその前年11月から数か月間のレイテ島が舞台。肉体も精神も極限状態に達した日本軍兵士らの姿が描かれる。
_同島を含むフィリピン諸島での戦没者は軍人・軍属だけで49万8600人(旧厚生省の集計)。その8割が餓死・病死者だったとの推計もある。
_揚陸したところを米軍機に空爆され、艦載の重火器も食料も失った生き残りの兵たちは、それでも大本営(天皇直属の指導部)に従い、密林超えの行軍を遂げようとする。
_主人公・田村一等兵もその中にいた。風貌はすでに中年だ。結核を患い、いつもせき込んでいる。本来は「もの書き」で、徴用(強制動員)された召集兵(補充兵)に過ぎず、小銃を構えてもサマにならない。やがて部隊は散り散りになる。はぐれた兵たちが飢えながら集まり、敵襲におびえながら暗闇で目だけをギョロつかせる。それは「餓鬼」を想像してしまうような姿だ。
_白昼、田村の見晴らす密林に白い煙(原作では「黒い煙」)が立ち上る。野火だろうか。クライマックスで塚本監督が観客に突きつけるのはまさに地獄絵だが、これが包み隠さない戦争の実情なのだろう。そこにも煙が立ち込めている。
_終盤には大半の登場人物が死に、田村だけが生還を果たす。でも幸運とは思えない。彼には、煙を嗅ぐたびに襲うフラッシュバックから逃れる術がない。
_終戦70年の夏。映画館を出て香ばしい煙ただよう住宅街に帰れる私たちは、幸福だ。
















