TOP >> WEBコンテンツ >> 全国映画よもやま話 >> ベルリン映画祭 日本映画は本当に好調か
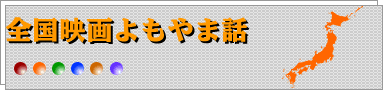
ベルリン映画祭 日本映画は本当に好調か
2017年3月20日 北海道新聞 朝刊
林瑞絵の欧州だより
ベルリン映画祭 日本映画は本当に好調か
邦画が好調と言われる。昨年は「君の名は。」「シン・ゴジラ」と大ヒットが続き、観客動員数は42年ぶりに1億8千万人を突破。先のベルリン映画祭でも荻上直子監督の「彼らが本気で編むときは」がテディ審査員特別賞を獲得するなど吉報が続く。だが邦画の中身も本当に好調だろうか。
国内向けに偏り
昨年の邦画の公開本数は610本。確かに数は多いが、羽振りが良いのは漫画やドラマが原作のガラパゴス化(国内市場向けに独自進化)した作品が主。演出はテレビ的な表現に流れる。だから400本と上映本数が多いベルリンでも選ばれる邦画は4本と映画大国としては少なめだ。
邦画のサポートでベルリン入りしたぴあフィルムフェスティバルの荒木啓子ディレクターは、邦画界に苦言を呈する。「まるで芥川龍之介の『蜘蛛の糸』。一人が成功すればみなが群がる。独立系の監督は『誰も助けてくれない』と腹を決めてやるしかない。生き残る監督はほぼいません」。当たれば一部の会社は潤うが、制作の現場はジリ貧状態で疲弊している。
数少ない「生き残り」の石井裕也監督は、東京に漂う不器用な若者の愛と孤独を描く「映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ」(札幌シネマフロンティアで5月27日(土)公開予定)をフォーラム部門に出品。最果タヒさんの詩集映像化に挑んだ作品は、2010年代の時代の空気を繊細かつ鮮やかに活写した逸品だ。「世界のどの街にいても感じる不安や居心地の悪さというのがある。そんな同時代性を東京にいながら掘り続ければ、海外と握手できると思った」と監督。上映後の会場の好反応からは、監督の思いが異国の地に届くのを感じた。
助成体制も不備
真の邦画文化が花開くためには、この作品のように類型化を拒める個性が必要だ。しかし日本の映画界は作家の個性に興味がない。国の助成システムも十分に機能しているか疑問が残る。日本は映画事業の案件ごとに「これは文化庁、これは経産省」と担当が変わる。フランスや韓国のように映画に特化した公的機関がなく、国が映画振興を一丸となり進められる態勢にない。補助金の流れも不透明だ。「クールジャパンの補助金は有象無象に食い尽くされ現場に届かない。映画に限らずどの分野でも公金を得るのにたけた人がいる。補助金をハンドリングできる人材がいないと無意味。」と荒木さん。昨今の公金横領疑惑の報道を見るにつけても、既得権益を放さぬ輩が跋扈する日本社会に暗澹たる気分に陥る。問題の根深さに目まいを覚えるが、まずは動員数という目先の数に惑わされず、現実を直視することから始めたい。(はやし・みずえ=映画ジャーナリスト)
















